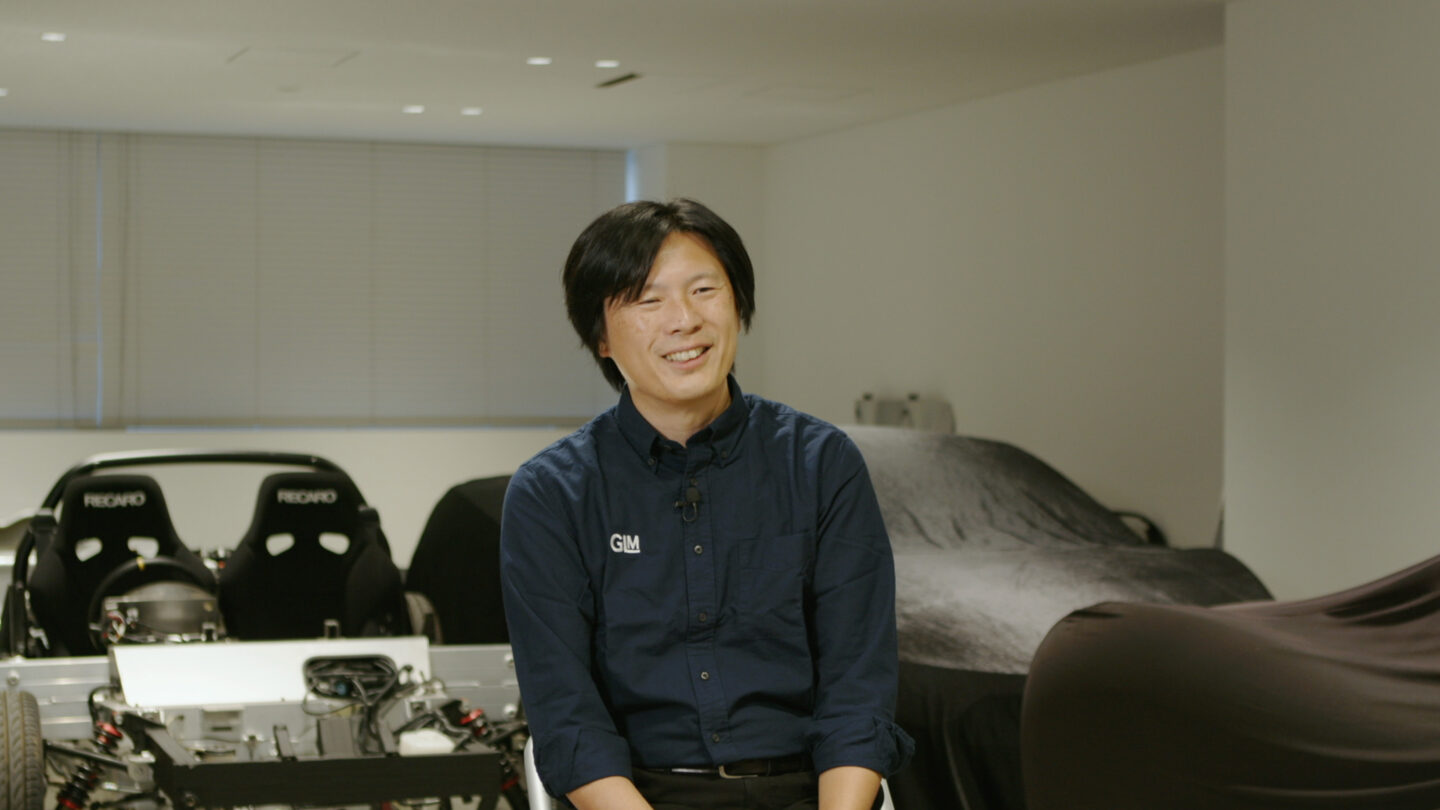- 開発エンジニアインタビュー
商用車向け車載用サブバッテリーの魅力を解説

現在、発売中の「商用車向け車載用サブバッテリー」について、その開発に携わったエンジニアの平野 晃敏と榎木 憲治より、プロダクトの特徴と開発エピソードを交えた本製品の魅力を解説してもらいました。

Q. どのような特徴をもったプロダクトでしょうか?
GLM 平野 晃敏(以下、平野):トラックドライバーさんが停車時にエンジンを止めて、思う存分、電力を使っていただける製品です。メリットとしては、トラックのエンジンをストップできるので燃料を大幅に削減できる点と、車両側の補機バッテリーは、容量が決まっているので、あまり使い切れないところがあるのですが、本製品では、容量がなくなるまで十分に使っていただけるので、安心してパーキングクーラーを使用できるプロダクトに仕上がっています。機能もとてもシンプルな構造に設計しているので、例えば、ドライバーさんがトラックのキーをオンにしたら勝手に充電が始まり、電力の使用がなければ自動でシャットダウンするといった機能を実装させていただいてます。

Q. 開発で苦労されたエピソードありますか?
平野:これまでのGLMのEV開発ですと、コンポーネントを用意して車両を仕上げて、お客様にお渡ししますが、今回はバッテリーユニットであったり、コントロールユニットであったり、基本的に直接お客様にお渡しするのではなくて、トラックを扱う架装会社さんにお渡しして、取り付けていただくので、あらゆるトラックに取り付けしやすい仕様に仕上げないといけない点は、簡単なようで苦労しました。
例えば、ナットですと、仕込みナットを事前に用意しておくのですが、トラック業界標準みたいな仕様に寄せておく必要があり、当初、そういった情報が全くなかったので、手探りでリサーチを行いました。トラックに取り付けるためには、どの辺りに?どんなサイズに?どんなナットを用意したらいいのか、業界的な通例や情報を、いちから調査しました。未だに迷う部分もありますが、キット化するにあたって、バッテリーを取り付けるブラケットについて自分たちで設計したのですが、一方で架装会社さんによっては、加工を自ら行われる会社さんも多くあり、意外と必要なかったりするので、どこまで用意すべきか難しいところではあります。

Q. これまでのEV開発が応用された点はありますか?
GLM 榎木 憲治(以下、榎木):リチウムイオンバッテリーのノウハウは十分に応用されています。作動するには条件が様々ありまして、熱だったり、突入電流だったり、その辺のところをEVで使っているリチウムイオンバッテリーの技術を応用しています。実際に走行させて温度上昇を確認したり、突然の電流で定格以上の電流値が流れると、それを阻止するための内部的な構造を自動車のEVの技術を使って転用しています。ただ、スケールとしてはEVと比べるとかなり小規模にはなります。バッテリー容量も小さく、EVの走行時の負荷に比べて、エアコンの使用時のバッテリーの抵抗はかなり小さくはなります。

Q. GLMならではのプロダクトの特徴はありますか?
平野:実はディスプレイのデザインが、トミーカイラZZ(以下、ZZ)のメーターデザインが踏襲されています。ZZのメーターデザインを担当したGK京都さんというデザイン会社に依頼して、他にも数パターン、デザインいただいたのですが、ZZのメータークラスターを彷彿させるデザインも作っていただいて、GLMの開発メンバーの中で多数決を行い決定しました。インターフェイスがZZ譲りになっています。

Q. 開発時に予想外だった点はありますか?
榎木:商用車の入力時の振動が予想を遥かに超えるほど大きな点に驚かされました。当初、想定していたよりも振動の入力が大きく、手直しをした部分はたくさんあります。これまでの乗用車の数値だとまったくうまくいかず、改めて調べてみると想定した数値よりも倍以上の衝撃振動が入っていたので、トラックのスケール感を改めて痛感しました。開発時にブラケットが破断したり、配線が断線するなど、そういったケースは、度々、みられました。商用車や貨物車は、目に見えて振動が大きなものでしたので衝撃的でした。そのため、走行テストはかなりの距離で行い、今のところ、きちんと対策をしましたので、問題は解消しています。主に部品の補強と、ハーネスの対策などです。

EVの車両開発ノウハウを基に、エンジニアの様々なこだわりと想いが注ぎ込まれた「商用車向け車載用サブバッテリー」。ぜひご活用ください。
当製品に関するお問合わせは、メールにて受付中です。
お問い合わせいただき次第、担当者より早急にご連絡させていただきます。